1.基準要件
◆労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
→前提条件ですが、雇用後も定期的に出入国在留管理局からのチェックが入るため遵守しましょう。
◆1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
→日本人も対象となりますので注意しましょう。
◆1年以内に行方不明者を発生させていないこと
→受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないか確認しましょう。(技能実習も含みます)
◆欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
→過去5年間に遡って確認しましょう。
◆支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
→支援にかかる費用を外国人本人に負担させることはできません。
◆外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ企業が認識して雇用契約を締結していないこと
→例えば、外国人本人の早期退職や失踪を防ぐために、あらかじめパスポートや金品を預かる行為はできません。
◆違約金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
→外国人本人の早期退職や失踪を防ぐために、違約金等を定める行為はできません。
◆報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
→銀行口座への振込が原則となります。
2.雇用契約の要件
◆分野ごとの省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
→特定技能の対象業種かつ該当の業務に従事させる雇用契約である必要があります。
◆直接雇用かつ、正社員での雇用であること
→飲食料品製造業/外食業分野での派遣社員での雇用はできません。
◆所定労働時間が、同じ受入れ企業に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
→同ポジションで雇用をしている日本人従業員と同じ条件である必要があります。
◆報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
→同ポジションで雇用をしている日本人従業員と同じ条件である必要があります。
◆外国人であることを理由として、待遇等に差別的な取扱いをしていないこと
→労働時間や給与だけではなく、その他の福利厚生なども日本人と同等である必要があります。
◆一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
→日本人雇用時と、同等の待遇が必要です。一時帰国の際の休暇取得できる日数や、繁忙期等で一時帰国が難しい期間がある場合、入社前に本人の理解できる言語で書面等で交わしておきましょう。
◆受入れ企業が外国人の健康や、その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることができること
→日本人同様に、健康診断を受信させることも必要です。
◆契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
→契約終了に伴い外国人が帰国する際は、帰国旅費は本人が自己負担できるよう措置を講じましょう。
3.雇用後の義務の履行
◆外国人と結んだ雇用契約を履行すること
→雇用契約通りに雇用をしているかどうかは入国管理局のチェックが必ず入ります。
確実に履行できる雇用契約にしましょう。
◆外国人への支援を適切に実施すること
→特定技能外国人の雇用後は義務的支援を行う必要があります。
◆出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
→特定技能外国人の雇用後は各種の報告業務を行う必要があります。
4.協議会への加入
特定技能外国人を雇用する場合、協議会に加入する必要があります。
協議会は16分野ある特定技能の各管轄省庁を中心に、特定技能外国人の適切な受入れや保護等を目的に組織されています。
飲食料品製造業と外食業は農林水産省管轄の、食品産業特定技能協議会への加入が必要となります。
なお、加入費用・年会費等は無料です。
参考:農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」
4-2.外国人側の要件・必要な資格
外国人側に必要な要件は下記のとおりです。
前述のとおり、外国人が「特定技能」の在留資格で働く方法は3つあります。
下記のいずれかを満たしている必要がありますので確認しましょう。
◆海外在住者が試験に合格していること
→技能評価試験(各業種ごとの試験)、日本語評価試験(全業種共通)の2つの試験に合格する必要があります。
◆国内在留者が試験に合格していること
→技能評価試験(各業種ごとの試験)、日本語評価試験(全業種共通)の2つの試験に合格する必要があります。
例)留学生が上記試験に合格
◆技能実習2号以上を修了していること
→技能実習2号もしくは3号を修了後、特定技能への移行ができるようになります。
特定技能へ移行する業務が技能実習で従事していた業務と関連性がある場合、試験は免除となります。
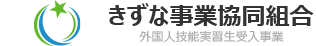

 お問い合わせ
お問い合わせ HOME
HOME